「銀行員と資格取得」
この関係は、切っても切れない関係と言えます。
厳しいようですが、銀行員はいくつもの資格を取り続けなければなりません。
特に若手のうちは、資格取得のために「常に何かの試験勉強をしている」という方が多いのではないでしょうか?
そんなやることが多く、平日も休日も忙しい銀行員のあなた、もしくはこれから銀行員を目指す方へ。
銀行に9年勤めた私が、優先して取るべき資格とおすすめの勉強方法について解説します。

【必須の3種】証券外務員・生命保険募集人・損害保険募集人

まず、銀行員として必ず取得しなければならない資格は、次の3種類です。
- 証券外務員資格 一種・二種
- 生命保険募集人資格 一般・専門・変額
- 損害保険募集人資格 一般
この3つは、金融機関で金融商品を販売するために必須の資格になります。
これらの資格はメガバンク、地銀、信金、信組など、金融機関の規模は関係なしに、どの金融機関でも必ず取得することになります。
以下で詳しく説明していきます。
なお、難易度は独断で、
★1つ…ほぼ勉強不要
★3つ…1-2ヶ月程度の勉強が必要(平日1時間&土日3-4時間を1ヶ月)
★5つ…計画的かつ数ヶ月単位の勉強が必要
このくらいの目安でご覧ください。
【証券外務員資格】一種はちゃんと勉強しないと落ちる
二種★★⭐︎⭐︎⭐︎(平日30分&土日2時間を1ヶ月)
一種★★★⭐︎⭐︎(平日1時間&土日3時間を1ヶ月)
証券外務員資格は、投資信託等の金融商品を取り扱う上で、必須の資格になります。
私の銀行では、入行前に外務員二種を取得するよう指示がありました。
この資格がないと、金融商品を一切販売できません。
証券外務員試験は、
「銀行員人生最初の関門」
になります。

二種は配布される問題集を一通り解いて、足りない部分はテキストを読めば合格できます。
一種は二種よりも難易度が上がり、同期の中でも不合格の人が出ました。一種は、落ちる人は2、3回落ちていました。
不合格になると業務時間中に受験しに行くことになり、かなり肩身の狭い思いをすることになります。
試験は甘く見ずに、一発で合格できるよう平日も含めて計画的に勉強時間を確保した方が無難です。
【生命保険募集人】一般・変額は余裕、専門は少し勉強が必要
一般・変額★⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎(平日30分&土日1時間を0.5ヶ月)
専門★★⭐︎⭐︎⭐︎(平日30分&土日1時間を0.5ヶ月)
生命保険募集人資格は、銀行の収益の柱でもある保険販売に関わってくるため取得は必須。
本部が申し込みをしてくれますので、テキストを自分自身で用意する必要はありません。
一般に合格すると、円建保険の提案・販売が可能となります。
専門・変額に合格すると、銀行が販売に力を入れている外貨建保険や平準払保険等の販売が可能となります。

専門では計算問題が少々入ってきます。
勉強の仕方としては、パターン化された計算問題をまず押さえて、その他の暗記項目を覚えていけばOK。
変額保険は範囲が狭く、勉強時間はほとんど必要ありません。
模擬試験を解いて解説を覚えるだけでよく、人によっては3日ほどで受かると思います。
専門と変額の労力の配分は、9:1で専門を優先しましょう。
【損害保険募集人】ほぼ勉強不要
★⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎(平日30分&土日1時間を0.5ヶ月)
ほぼ勉強不要な資格です。人によっては一週間もかからずに受かります。
生保と同じく、テキストは本部が申し込むので自身での購入は不要です。
試験はパソコンでの受験になります。

画面にテキストが表示されて、見ながらの解答が可能です。
もし答えを忘れてしまっても、テキストのどの辺りに書いてあるかさえ覚えていれば全問正解も可能です。
合格率は9割を超えるので、必ず一発合格したい資格です。
【昇格に必要】簿記・FP・宅地建物取引士・銀行業務検定・内部管理責任者
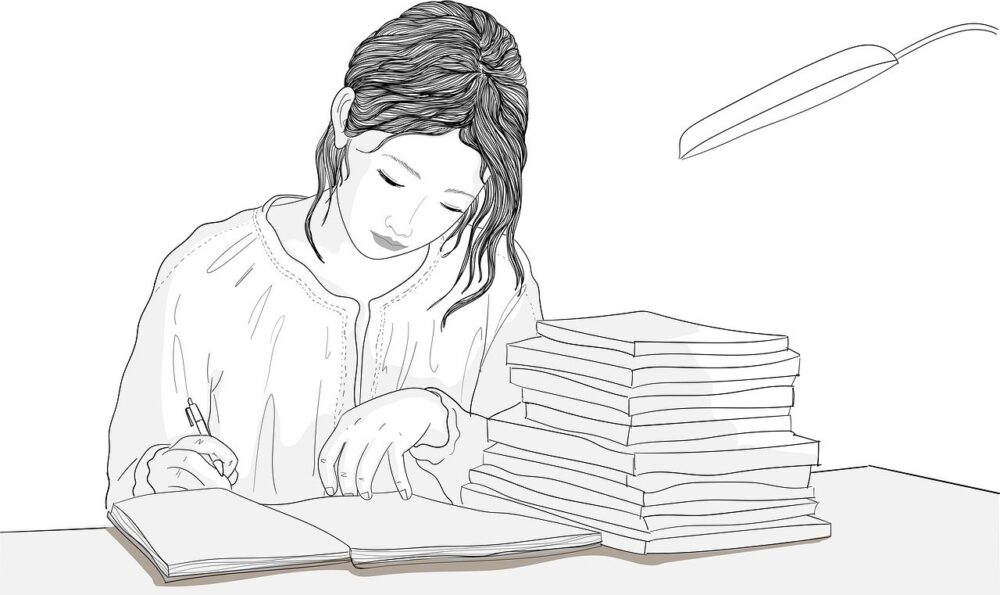
ここからは必須ではありませんが、主に昇格条件となっていることが多い資格になります。
おすすめの順番で言うとこの通り。
- 簿記3級、2級
- FP3級、2級
- 宅地建物取引士(宅建)
- 銀行業務検定試験 法務・財務・税務 各3級、2級
- 内部管理責任者(内管)
これらの資格を取得できるかどうかで昇格の速さにも影響します。
ある意味、上司や人事部から試されていると思ってください。
言ってみれば昇格試験ですね。
では、取得をおすすめする順に解説します。
コツコツ勉強する習慣を身につけるために「簿記3級」から
★★★⭐︎⭐︎(平日30分&土日4時間を3ヶ月)
この中でまず取得すべきは簿記3級です。
1年目は証券外務員や生保・損保資格で忙しいですが、正直言ってこれらの資格は受かって当たり前。
無事合格したら簿記とFPの勉強を始めましょう。
コツコツ勉強する習慣を身につけるために、まずは簿記から勉強することをオススメします。

簿記は手軽に取れて、最もコスパの良い資格。
銀行員として生きていく上で、数字や決算書の情報を把握して、企業を分析するスキルは必須となります。
簿記の知識に触れておくと決算書の理解が早くなり、経営者との面談の際、決算書を一目見るだけである程度の質問ができるようになります。
簿記3級では、以下のような基本的な知識を問われます。
- 仕訳
- 勘定科目
- 貸借対照表
- 精算表
簿記では電卓を使用しますが、業務でも必ず必要になるのでこの際に購入しましょう。
電卓を選ぶポイントはこちら。
- 予算:可能なら5,000円〜8,000円くらい
- 12桁を選ぶ(12桁=1,000億)
- 派手な色は選ばない
- 高級機は押し心地がよく耐久性が高いので結果として得
- 簿記2級を受ける人は「日数・時間計算」機能付きを選択
12桁あれば普段の業務でも余裕です。
色は「白」「黒」「グレー」「紺」などが落ち着いていて、長く使えるのでおすすめ。
長く使うことを考えて、できれば予算は5,000円くらい出したいところ。
高級機は以下の特徴があってストレスが少ないです。
- ボタンの押し心地がよい
- ボタンを押す音が静か
押し心地がよく押し間違いが格段に減るので、毎日のストレスがかなり減ります。
金融電卓を客先で使うことはほとんどなく、その分の予算を普段使用する電卓に充てる方が幸せになれます。

金融電卓を買うくらいなら、その予算をぜひ普通の電卓に回してください。
試験には使い慣れた電卓を使用できるように、早めに購入し業務で使用して慣れておくことをおすすめします。
簿記は慣れるまでに少し時間がかかりますが、覚えて問題が解けるようになると途端に楽しくなります。
【FP3級or2級】役に立つし何より面白い
★★★☆☆(平日30分&土日3時間を2ヶ月)
FP(ファイナンシャル・プランナー)では、お金と暮らしに関わる幅広い金融の知識が得られます。

目安として、2年目までに取得しておきたい資格です。
相続や年金などお金にまつわる内容のため、勉強すればするほど自分にも役立つ内容です。
コスパが良く、業務だけでなく自分自身にも非常に役立つ資格。
主に個人客や法人役員を相手に資産運用の提案をする際にFPの知識が生きてきます。
出題範囲は、生命保険、年金、相続など多岐に渡ります。

3級は基本的な問題が多く、難易度は易しめ。
勉強時間があまり確保できなくても、一般常識や現在の知識で解ける問題も多いです。
FP2級は、より具体的な資産運用の提案に対する知識が身につきます。
こんな人は3級を飛ばして2級を受験しましょう。
- 勉強時間を節約したい人
- より深い知識を身につけたい人
- 提案先が個人の資産運用・相続が中心の人
合格すると「ファイナンシャル・プランニング技能士」の称号を名刺に入れることができます。
【宅地建物取引士(宅建)】できれば5〜7年目までに取得しておきたい
★★★★⭐︎(平日1時間&土日4時間を4ヶ月)
簿記やFPと比べると難易度が上がりますが、不動産に興味がある人は早めに挑戦したい資格です。
銀行員は富裕層相手にもセールスを行うため、不動産の知識も求められる機会が多いです。
内勤の方も営業の方も、どちらも今後不動産会社の担当者とやり取りをする機会があります。
名刺に「宅地建物取引士」の文字があると相手の担当者も一目置かれます。
一通り資格を取得できた頃、目安で言うと5〜7年目辺りで受験を考えてもいいでしょう。

宅建の魅力は、転職の際の履歴書にも書けること。
宅建を持っていると不動産業界にも選択肢広がるため、可能であれば取得しておきたい資格です。
魅力的な宅建ですが、個人の環境にもよりますが勉強時間の目安は「300-400時間」と言われています。
この時間を平日の仕事終わりと休日に全て勉強しようとすると、「1日2時間×180日=360時間」くらいかかる計算になります。
これだけの勉強時間を確保するのは、なかなか難しい人も多いのではないでしょうか。
そこで必要となるのが、「スキマ時間の活用」と「効率的な勉強」です。
スマホで学べる資格試験のオンライン講座「資格スクエア今や資格の勉強も動画を利用する時代です。
youtubeにも宅建の動画はありますが、こちらの講座は講師の方の解説がわかりやすくてインプット講義が76時間分とボリュームも多くてかなり良心的。
宅建の取得を考えている方は、10本の無料講義とフルカラーのサンプルテキストを見て、雰囲気を確認してみるといいです。
※関連記事
「銀行業務検定試験」は業務に慣れてきた頃に受けよう
3級★★⭐︎⭐︎⭐︎(平日30分&土日1時間を2ヶ月)
2級★★★⭐︎⭐︎(平日30分&土日3時間を3ヶ月)
おそらく支店の中で研修担当役席になっている上司から「受けろ、受けろ」と何度も言われることになる試験です。
ただ、「銀行業務検定試験」は銀行にいる間しか役に立たない資格の代表格。

簿記やFPを優先して、銀行業務検定は後回しでよし。
後回しで良い理由は、法務・税務の各3級の内容は、日々の業務の中に自然と組み込まれているから。
日々の業務の積み重ねが試験対策につながります。
業務に慣れてきた頃にまずは3級から受験することをおすすめします。
3級の難易度は人によりますが、過去問を頑張って3周くらい解けば合格できます。
業務に慣れてきた頃には3級の内容も頭に入りやすくなっているため、3級だけ取得してあとは他の資格に時間を割くべきです。
内部管理責任者(内管):優先順位は低め
★★⭐︎⭐︎⭐︎(平日30分&土日1時間を1ヶ月)
内部管理責任者は、日本証券業協会が定める民間の資格で、各支店の取引やその管理体制が適切かどうかをチェックする立場の人を言います。
主に預金の課長や副支店長がそのチェックをする場合が多く、管理職になるまでに取得が必須となっている場合が多いです。

試験の難易度は低めです。
コンプライアンスや普段の業務で聞く用語を理解していれば、一般常識でも回答可能な問題が多いです。
こちらも優先すべき資格でないため、FPと簿記を先に取得し、その後に受験するくらいで良いです。
【転職に有利】FP1級・簿記1級・証券アナリスト・中小企業診断士

これらの資格は、取得すると銀行員以外でも活躍の可能性が広がる資格です。
- FP1級
- 簿記1級
- 証券アナリスト
- 中小企業診断士
勉強時間の確保が大変かもしれませんが、知識と業務の幅が広がるだけでなく、銀行によっては報奨金が出たり、将来的に銀行以外の分野への転職も視野に入ります。
まずは、優先順位の高い資格から取得をしていき、自分の興味・適性にあった資格にチャレンジしてみると良いです。
【勉強方法】スキマ時間に動画で勉強するのがおすすめ

今の時代、分厚い参考書を使って勉強したり、重い参考書を持ち歩いたりする必要は無くなりました。
当時の私は参考書を使って勉強しましたが、今は通勤時間やスキマ時間に動画で効率的にインプットをして勉強するのが主流になっています。
あなたも、動画であれば気が付いたらかなりの時間観てしまったということも多いのではないでしょうか?
スマホで学べる資格試験のオンライン講座「資格スクエア
動画なので、理解と定着がしやすく、続けやすい。
通勤中やスキマ時間に勉強しやすく、まとまった勉強時間を確保しにくい人でも着実に勉強できるのでオススメです。
特に朝の通勤中に動画でインプットする習慣を身につけると、ライバルとの差はかなりのものになります。
動画でスキマ時間を有効に使って、効率的かつ着実に勉強したい方にオススメです。
【まとめ】将来を見据えて計画的な資格取得をしてほしい
当記事では、銀行員が取得するべき資格について、優先度が高い順にご紹介しました。
業務上必須の資格から昇格に必要なもの、または自身のステップアップになる資格など、様々な資格があります。
転職するしないに関わらず、将来を見据えた計画的な資格取得をおすすめします。
勉強時間の確保はもちろんですが、勉強効率が非常に大切になってきます。
自分1人で勉強を進めるのも大事ですが、動画などの専門のサービスを活用することで失敗するリスクを下げることができます。
不合格になって気持ちが萎えてしまうリスクを考えると、オンライン講座への投資はかなり有効な選択になると考えます。
この記事が銀行員の方や、これから銀行員を目指す方に少しでも役立つことを願っています。
以上






コメント